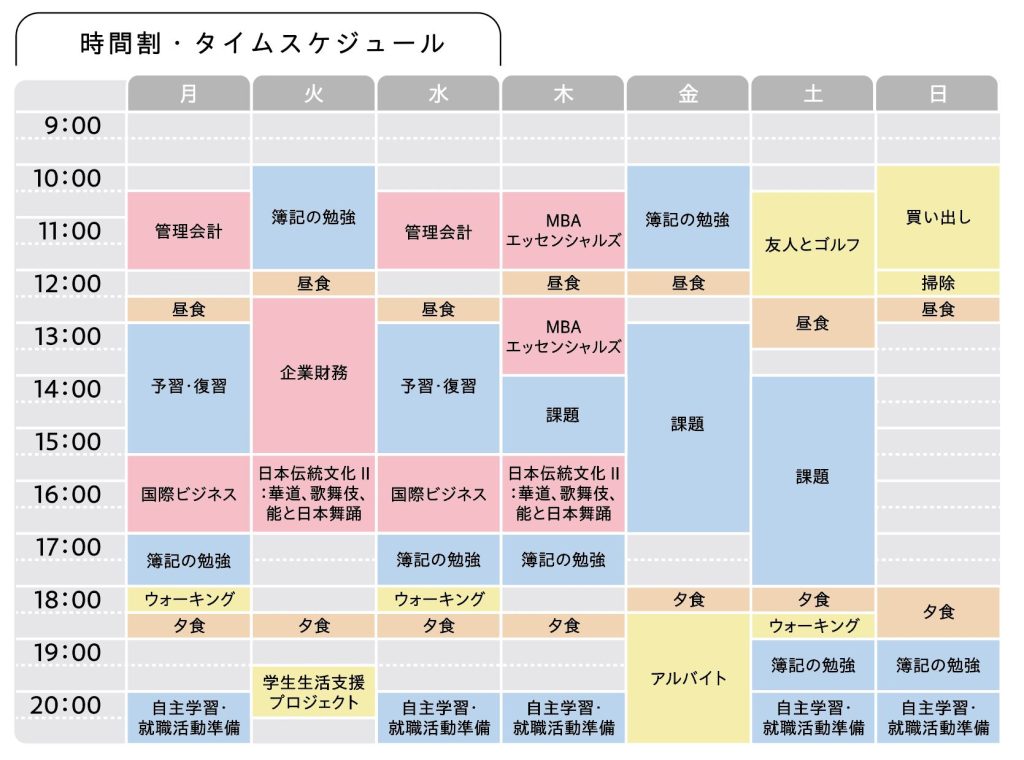教養専門科目群
グローバル・ビジネス領域
Global Business Program: GB
創造力、批判的思考力、そしてグローバルな視点を養う
グローバル化の進展により、企業活動は拡大・複雑化の度合いを増しています。変化が加速し、不確実性が増していく現代において、企業が社会に有用な財・サービスを持続的に提供していくためには、ニーズを地域規模、そして地球規模で的確に把握しつつ戦略を策定しなければいけません。本領域では、これに対応すべく経済学およびビジネスを中心に幅広い教育を提供し、創造力、批判的思考力、そして、グローバルな視点を備えた人材を育成します。
教員からのメッセージ
バランスのとれたグローバルビジネス教育で未来へ
グローバル・ビジネス(GB)領域は、ビジネス分野において必要とされる専門知識に加え、リベラルアーツ教育を融合し、一般的なビジネス課程とは一線を画したカリキュラムを提供しています。批判的そして創造的な思考、問題解決のための専門的なアプローチ、コミュニケーションスキル、ビジネスの意思決定の背景にある文化的・歴史的側面の理解を深めることに重点を置いています。これらのスキルは、学生の将来のビジネスキャリアにおける長期的な成長に不可欠なものだと考えているからです。

本領域では、会計、ビジネス文化、経済、金融、法律、経営、マーケティング、定量分析、サステナビリティなど、ビジネス分野の初歩から応用までの科目群を開講し、ビジネスの基礎を築きます。教員は国際的・学際的な視野に立ち、対話型の授業を展開しながら、学生の積極的な授業参加を促します。学生は、多様で豊かな学修環境の利点を生かし、互いの意見から学び合っています。本領域の教授陣は優れた教育者であるとともに、各分野で活躍する研究者です。また、ビジネス分野において豊富な経験を持つ人材も揃っています。
本領域での学びは、学生の将来にどのような影響を与えるのでしょうか。広い視野と職業人としての確固たる基盤を確立した卒業生は、国際競争力を持って、デジタル技術の進歩、グローバル化、環境におけるサステナビリティへの懸念といった将来の大きな課題に斬新な発想で対処していくでしょう。ビジネスは、現代社会と豊かな生活のあらゆる側面に影響を与えています。世の中で下されている経営判断が人や社会にどのような影響を与えるかをよく理解することは、学生自身の将来においてのみならず、豊かな社会を創り上げていくうえでも大変重要です。
※ここでは、英文メッセージの日本語訳を掲載しています。
クリントン・ワトキンス Dr. Clinton WATKINS
グローバル・ビジネス領域長/教授
学生インタビュー
吉田 容(石川県/2019年入学)
本学への志望動機は?
東日本大震災直後、災害時のペットの悲惨な避難状況を目の当たりにし、そこからボランティア活動を始めました。「動物愛護後進国である日本を発展させるために『自分なりの』貢献の仕方を見つけたい」と考えるようになっていたなかで、AIUのギャップイヤー入試を知り、オープンキャンパスに参加しました。すべて英語の模擬授業を受講したり、在学生の留学体験を聞くことができ、自分の将来の目標のために必要な力を伸ばすために最適な環境だと感じました。また、24時間利用できる図書館や竿燈会の活動など、AIU特有の生活環境に魅力を感じ、受験を決意しました。

特に印象に残ったGB領域の授業は?
「ECN310 会計学」です。会計学は、単に数字の学習ではなく、その背景にある幾多の人間の関わり合いについての学問です。企業が行っている活動に焦点をあて、異なる業種や業態のビジネスを理解するコミュニケーションツールとして存在する会計学に、面白さを感じました。さらに国や企業によって、会計に対する考え方・基準が異なるという点にも会計学を学ぶ楽しさを感じました。
AIUを目指す皆さんに伝えたいこと
「There is no way around the hard work, embrace it.(努力に逃げ道はない、努力を愛せ。)」は、私の尊敬する、2022年に引退したテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラー氏の言葉です。
AIUでは多種多様な学びの機会がある分、自身の探究心を追求して主体的に行動することが大切だと感じます。皆さんにも、楽しんで努力し続ける姿勢を大事にしてほしいです。